親が高齢になると、所有している不動産の管理や活用について話し合いが必要となるケースがあります。特に認知症が進んでしまう前に、次の世代へスムーズに承継していくことは多くの方が考える課題のひとつです。
本記事では、親が持つ物件を“任せたい”と言ってきたときの選択肢や、それぞれの制度のポイント・リスクなどを解説します。後々のトラブルを防ぐためにも、どのような手続きをするのが最適か、一緒に整理していきましょう。
あらためて不動産管理を見直す機会を持つことで、親の将来の生活を安定させながら、家族間のトラブルを回避することにもつながります。次世代へのスムーズな引き継ぎを目指すために、必要な手続きを正しく理解していきましょう。
今後を見据えて持ち家や不動産を認知力があるうちに次の世代に承継したい人は少なくない
親の認知機能がしっかりしているうちに、財産を次の世代に引き継ぎたいと考える人は少なくありません。その背景や実情について確認します。
高齢化が進む中、自宅や投資用不動産をスムーズに次世代へ渡したいと考える家族は増加傾向にあります。理由のひとつとして、認知症による意思能力低下が進むと、法律行為が制限されるため、財産の管理や処分が円滑にできなくなるリスクが高まるからです。
また、不動産は流動性が低く金額も大きい資産であることから、日頃から誰がどのように管理していくかを決めておく必要があります。特に将来の相続に関して、親が望む形で資産を活用・承継するためには、事前の計画と手続きが大事になります。
このような準備をすることで、親自身も「いざという時にどうなるか」という不安を軽減できます。家族としても、意思確認ができるうちにリスクと対策を話し合い、最善の方法を探ることが重要といえます。
認知症の人の所有する住宅は2021年で220万戸超!ますます増加傾向にある
認知症によって判断能力が低下すると、自宅や投資物件などの管理ができなくなり、家族が代わりに売却や運用の手続きを進めることが難しくなりがちです。こうした事情から、認知症の人が所有する住宅の数は社会の高齢化とともに増えてきています。
売却や賃貸など雑多な手続きを進めるには、所有者本人の意思表示が必要になることが大半です。そのため、認知能力が不十分になると不動産の活用だけでなく、資産の保全にも支障が出る場面が増えてきます。
こうした状況を避けるためにも、できるだけ早めに財産管理の方法を親子間で取り決めておくことは非常に重要です。税金や制度の仕組みを理解しておくことで、後々のトラブルを最小限に抑えることができます。
認知症の人が不動産を保有したままにしておくことのリスク
所有者が認知症になると、不動産の売却や管理などの手続きがスムーズにできなくなる恐れがあります。そのリスクを整理してみましょう。
認知症によって所有者の意思能力が失われると、不動産の現状把握や意思決定が誰の権限で進められるのかが大きな問題となります。売却や修繕、契約更新などもしづらくなり、住まいの劣化や資産価値の低下につながることも少なくありません。
さらに、相続や税金の問題が発生した場合、付随する手続きが止まってしまう可能性もあります。特に、認知症が進んでからでは法的に有効な書類を作成することが難しかったり、後見制度の利用に時間や手間がかかったりするケースもあります。
このようなリスクを未然に防ぐためには、元気なうちから家族で話し合いを行い、どの制度を使うか検討することが大切です。将来的にどのように財産を管理し、誰が判断を行うのかを決めておけば、混乱を最小限に抑えられます。
物件を任されたときにできる選択肢
実際に物件を親から任されたとき、どのような手段を選ぶことができるのか、概観を紹介します。
まず考えられるのが、家族信託契約、成年後見制度、任意後見制度といった法的手段による管理方法です。それぞれ手続き方法や適用範囲が異なり、親の希望や家族の負担感によって向き不向きが存在します。
たとえば、意思能力があるうちから契約内容を細かく決めておきたい場合には家族信託や任意後見制度が選択されることが多いでしょう。一方、すでに認知機能が低下している場合は、成年後見制度を利用して財産を保護する方法が適切です。
また、生前贈与という形で財産を早めに移転し、相続時の手続きを簡略化する選択肢も考えられます。どの制度でも一長一短があるため、費用面や家族の状況、親の希望を擦り合わせながら丁寧に検討することが重要です。
家族信託契約をする
柔軟に財産管理をする方法として注目されている家族信託の概要や利点・欠点について知っておきましょう。
家族信託は、親(委託者)が子などの受託者に財産の管理・処分権限を託す仕組みです。成年後見制度と比べて自由度が高く、認知症による意思能力の低下後でも受託者が不動産を活用・売却できる点が特徴的です。また、名義移転に関しても贈与税が発生しない形で管理権限を移すことが可能です。
ただし契約の内容をしっかり取り決め、信託の趣旨や分配方法などを公正証書に盛り込むことが必要になります。家族間の合意形成が前提となるため、時間をかけて制度設計を行い、それを契約書に落とし込むプロセスが欠かせません。
信託財産に含まれる不動産の処分権限や活用目的を明確に定めることで、後々のトラブルを回避できる可能性は高まります。一方で、相続が二次・三次にわたる場合や、長期におよぶ信託管理に伴う受託者の負担など、家族信託を始める前に考慮すべき点はあります。
家族信託とは
家族信託とは、財産を信頼できる家族(受託者)に信託することで、管理や処分の権限を委託者本人に代わって行えるようにする契約です。名義上は受託者に移りますが、贈与や相続とは異なり、あくまで信託目的を達成するために権限を与えるという位置づけになります。
委託者が認知症などで意思能力を失っても、信託契約で定めたとおりに財産を取り扱うことができるのが大きなメリットです。例えば、売却や賃貸の手続きも受託者が自由に行えるため、資産の有効活用が妨げられにくくなります。
また、家族間であっても第三者による悪用を防ぐためには、契約書の内容を公正証書として明確化することが望まれます。公証人役場で手続きをすることで、親族間の口約束に終わらず法的に実効性のある契約を作ることができます。
家族信託のメリット
家族信託の最大のメリットは、認知症などによる意思能力の低下があっても、受託者が不動産の売却や管理を続けられる点です。これは成年後見制度よりも自由度が高く、目的に沿った不動産活用ができるという特徴をもたらします。
また、贈与税や不動産取得税がかからない形で名義を移すことができるため、節税メリットもあると理解されることが多いです。ただし、実際には契約内容や信託の目的によって扱いが変わる場合があるため、専門家に確認することが重要です。
さらに、財産の行き先を二次相続、三次相続まで指定できるため、家族が受益者となる順番や条件を細かく決められます。これにより、複雑な家族構成の場合でも、長期的に安定した資産管理・承継の仕組みを構築しやすくなります。
家族信託のデメリット
家族信託には専門的な知識が必要であるため、契約内容の設計や公正証書の作成にかかる費用が比較的高額になるケースがあります。信託財産の登記変更などの手続きも必要で、司法書士や税理士など専門家のサポートが不可欠になることも多いです。
また、長期間の契約となる場合が多いため、受託者のライフイベントや家族間の状況変化にも対応が必要になります。たとえば受託者の健康状態に変化が生じたり、相続関係に予期せぬ変化があったりすると、再度契約内容の見直しが必要になってくるかもしれません。
さらに、信託は資産が委託者本人のところには戻らない仕組みになる面があり、契約を解除するには複雑な手続きが発生することもあります。信託の途中解約は難しくない場合もありますが、契約の条項によっては制約が多い場合があるため、慎重な検討が重要です。
家族信託を相続対策で活用するポイント
相続が複数の世代にわたって発生する場合、従来の方法では都度相続人の合意を取り付けなければなりません。しかし家族信託であれば、二次・三次にわたる相続先をあらかじめ定めておくことができ、意向に沿った資産の受け渡しを実現しやすくなります。
また、遺言書と異なり死後だけでなく生前から財産管理を受託者に任せることが可能なため、親が高齢になっても物件を有効活用できる仕組みを柔軟に設計できる点が大きな利点です。
ただし、受益者や受託者が途中で変わる可能性もあるため、契約内容に変更条項を盛り込んだり、その際の手続き方法をあらかじめ取り決めておくことを忘れないようにしましょう。
家族信託のやり方
家族信託を始めるには、まず家族間で財産の扱い方や分配方法、管理の権限範囲などを話し合い、合意内容をもとに信託契約書を作成します。契約書の作成は法的に正確な記載が求められるため、公証人や司法書士などの専門家に相談するのが望ましいでしょう。
次に、公正証書として契約を残すことで、トラブル発生時のリスクを低減できます。特に不動産は登記も必要になるため、信託登記の手続きについても専門家と連携することが重要です。
最終的に、契約書が有効に成立した後、受託者は信託財産となる不動産の管理・運用を担います。信託契約で定めた範囲内であれば売却や賃貸の判断を下すことも可能となり、家族のために資産を有効活用できます。
成年後見人制度を利用する
所有者に認知症などの症状がある場合、成年後見制度を活用して財産管理を行う方法があります。
すでに認知症の症状が進行しており、意思能力が不十分と判断される場合は、成年後見制度で財産管理者を選任するのが一般的です。家庭裁判所の関与のもと、後見人が不動産をはじめとする財産全般を守る立場になります。
成年後見では、親の所有する不動産を売却したり、貸し出したりする場合でも、後見人が手続きを進めることができます。ただし、家庭裁判所への申立や許可など、一定の法的手続きが必要であることを理解しておく必要があります。
家族信託とは異なり、判断能力を失ったあとでも利用できる反面、細やかな裁判所の監督下に置かれるため、資金の使い道や財産の処分において厳格な手続きが求められます。この点は制度を選ぶ上での大きなポイントとなります。
成年後見人制度とは
成年後見人制度は、判断能力が低下した人の財産や日常生活を法的に保護するための公的制度です。家庭裁判所が選任した後見人は、本人の代わりに契約や手続きを行い、財産を管理・保全します。
活用のタイミングとしては、認知症などが進行して意思決定が難しくなってきた場合が典型的です。後見人は財産だけでなく、生活全般における保護・支援にも関与することができます。
なお、後見人が決まると、本人の財産は後見人を通してのみ処分・運用できるようになるため、家族でも勝手に売買や賃貸の契約を進めることはできなくなります。
成年後見人制度のメリット
成年後見制度は家庭裁判所の監督下にあるので、後見人が不正に財産を処分するリスクが低いというメリットがあります。もし問題が起こっても、家庭裁判所が後見人を解任し、別の人を選任できる仕組みが整備されています。
不動産の管理や売却も後見人によって法律的に正当に行われるため、契約をめぐるトラブルが生じにくい点もプラスです。また、後見対象となる本人の生活費や医療費などを確実に支出できるように、裁判所が監督します。
さらに、手続きが適切に行われる限り、親族同士の対立が起こりにくいのも特徴です。公的なチェック機能があることで、公平かつ透明性の高い運用が期待できます。
成年後見人制度のデメリット
手続きに時間と費用がかかる点がデメリットとして挙げられます。家庭裁判所に申立を行い、鑑定費用や専門家への報酬が発生する場合もあるほか、申し立てから後見人選任までに数カ月程度かかることもあります。
また、成年後見制度を利用中は財産の活用や運用について裁判所の許可が必要な場合があり、自由度が低くなる面があります。家族が独自の判断で売却や投資を行うことはできず、慎重な確認を経る手続きに時間がかかるかもしれません。
さらに、一度後見が開始されると、本人の判断能力が改善しても制度を終結するには裁判所の手続きが必要です。回復が困難なケースが多い半面、ごく一部を除いては長期的に後見体制が継続されます。
成年後見人になるには
成年後見人になるためには、家庭裁判所へ申立を行う必要があります。申立人は本人の配偶者や親族、または利害関係を有する人などが該当するケースが多く、医師の診断書や必要書類を準備して手続きを進めます。
裁判所が申立を受理すると、後見開始の要件が整っているか審査され、後見人を選任するためのプロセスがスタートします。親族が後見人になれる場合もあれば、状況によっては弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることもあります。
後見人に選任された後は、法定後見人として家庭裁判所の監督のもと、対象者の財産を管理します。報酬は家庭裁判所が決定する点も押さえておくべきポイントです。
任意後見人になる
将来の判断能力の低下を想定して、あらかじめ契約を結ぶ任意後見制度について紹介します。
成年後見制度はすでに本人の意思能力が衰えたケースに対応する制度ですが、任意後見制度は「まだ元気なうち」に将来を見据えて後見契約を結ぶ仕組みです。本人の意思がはっきりしているタイミングで契約内容を取り決められるので、ある程度自由度の高い財産管理が期待できます。
この制度では、将来、認知症などで判断能力が低下したときに備え、あらかじめ「任意後見人」に誰を選ぶか、どこまでの権限を与えるかを細かく決めておくことができます。実際に意思能力が低下し、家庭裁判所が開始を認めると、任意後見契約が効力を持ちます。
家族信託との大きな違いは、不動産の処分管理などについて一定の自由度が保たれつつも、後見制度という形で公的に保護される仕組みがある点です。とはいえ、契約内容によっては柔軟に対応できる場合とできない場合があるため、事前の検討が欠かせません。
任意後見人とは
任意後見人とは、本人がまだ判断能力を保っている間に、将来の財産管理や生活支援を行う人として契約で指定された人物のことです。契約書には、後見人が行える行為の範囲や物件の管理方法などを詳細に定めます。
任意後見人は、本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所の手続きによって正式に「任意後見監督人」が選ばれた後、職務を開始することになります。監督人は後見人の行動をチェックし、不正やトラブルを未然に防ぐ役割を担います。
これにより、家族だけで意思決定するよりも客観的な目が入るため、公平性や法的安定性が保たれやすくなる点が特徴です。
任意後見人のメリット
任意後見契約は、本人が自らの意思で契約を結ぶため、事前に細かい希望を反映できます。たとえば、住まいの管理をどのようにしてほしいのか、財産をどの程度自由に使っていいのかなどを具体的に決められるのです。
また、本人に意思能力が残っている間は柔軟に契約内容を変更することが可能で、その後の状況に合わせて微調整を図ることもできます。こうした柔軟性は法定後見にはない大きなメリットと言えるでしょう。
監督人の関与があるので、不正利用や定期報告の不備などが起こりにくい構造になっており、安心感が高い点も利点の一つです。
任意後見人のデメリット
最も大きなハードルは、実際に任意後見契約を開始するには家庭裁判所の手続きが必要であり、ある程度の経費と時間を要することです。また、契約を公正証書として残すために公証役場での費用も発生します。
さらに、契約を結ぶ時点で意思能力があると判断されないと契約自体が無効となる疑いがあります。そのため、ぎりぎりまで先延ばしにすると結べなくなる可能性があります。
また、一度開始されると監督人の報酬の負担などが継続的に発生し、自由に財産を処分するにも一定の制約が生じるなど、コストと自由度のバランスも検討ポイントとなります。
任意後見人のなりかた
任意後見契約を締結する場合は、公証役場で公正証書を作成する必要があります。契約書には、後見人に与える権限、管理する財産の範囲、代理権の内容、報酬などを明確に記載することが大切です。
いざ本人の判断能力が低下してきた段階で、任意後見の開始を家庭裁判所へ申し立てます。家庭裁判所が開始を認めると、監督人が選任されて正式に任意後見人が活動を始める仕組みです。
必要書類や手続き方法は地域によって若干異なる場合があるため、最初の段階で専門家に相談して進めるのがおすすめです。
生前贈与をする
相続への対策として、生前に不動産を贈与する方法を選択するケースもあります。その仕組みや税制を見てみましょう。
生前贈与とは、親が元気なうちに財産を子や孫に渡す方法の一つです。不動産であれば名義変更を行い、将来的な相続財産を減らすことで相続税の節税や、遺産分割の手間を軽減できる場合があります。
一方、贈与によって不動産を移す際には贈与税が課される可能性があるため、どのような制度を利用して贈与するかが非常に重要です。一般的には暦年贈与や相続時精算課税制度などが有名ですが、どちらを選ぶかは親の資産状況や将来像によって異なります。
生前贈与を行う場合、親の生活資金への影響や、あとから贈与自体を取り消しにくい点にも注意が必要です。家族全員が納得できる形になるかどうかをよく話し合うことが欠かせません。
生前贈与とは
生前贈与は、故人が亡くなった後に発生する相続ではなく、生きているうちに財産の全部・一部を無償で渡す行為を指します。不動産の場合、名義変更に伴う登記手続きや贈与税の申告が必要になるのが一般的です。
生前贈与によって、受贈者(贈与を受ける人)は早期に資金や不動産を有効活用できます。また、贈与時に贈与税を支払ってしまえば、相続時にはその財産が課税対象とはならないため、相続税対策として取り入れられることがあります。
ただし、贈与した財産は取り戻しが原則難しいため、親が適切な生活費を確保できるかどうかも重要な検討事項です。
普通の贈与との違い
生前贈与は単なる贈与の一形態ですが、特に税制優遇との関連で注目されています。一般的な贈与はいわゆる暦年課税と言われ、年間110万円の基礎控除を活用できますが、一定額を超えると贈与税が高率で課税されます。
一方で、生前贈与においては相続時精算課税制度など、相続と贈与をセットで考える制度が用意されており、これを利用すると贈与税の負担が一時的に抑えられるケースもあります。
つまり、普通の贈与として取り扱うか、生前贈与の特別な制度を使うかによって、実際に納めるべき税額や手続き方法が大きく変わる点が最大の違いです。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は、贈与額が2,500万円までなら贈与時に課税が猶予され、最終的には相続時にまとめて精算する制度です。高額な財産を生前に移転したい場合に検討されることが多い仕組みです。
通常の贈与税率よりも有利な場合があり、親がまとまった不動産を子に渡す際によく活用されます。ただし、2,500万円を超える部分には贈与税がかかるため注意が必要です。
また、相続時にその贈与財産を含めて課税額を計算するため、結果的に税負担が大きくなる可能性がある点も理解しておかなければなりません。
相続時精算課税制度のメリット
通常の贈与税率では大きな負担が生じる規模の不動産を渡す場合でも、一時的に贈与税の支払いを低く抑えられます。これにより、親が資産を効率よく移転し、子が早めに活用できるメリットが生まれます。
また、特定の親子間など、相続時精算課税の対象になる関係性であれば利用しやすい制度です。年齢条件などの要件を満たせば大幅な節税効果を得られる可能性があります。
結果的に相続時にまとめて課税されるとはいえ、贈与税の納付が繰り延べされるため、得られた資金や不動産を活用しながら、先々の相続に向けたより柔軟なプランを立てることができるでしょう。
相続時精算課税制度のデメリット
相続時に結局まとめて課税されるため、相続税の合計額が思った以上に大きくなる場合があります。制度を利用したからといって、必ずしも最終的な税負担が軽くなるわけではありません。
いったん制度を選択すると、通常の暦年贈与の基礎控除の適用ができなくなるなど、取り消しが難しくなるのも注意点です。制度を使うかどうかは、綿密なシミュレーションが必要です。
また、贈与した不動産の名義を移した後でも、相続時まで管理をどうするかが問題になるケースがあります。事前に管理体制を考えておかないと、親が想定外の出費を余儀なくされるかもしれません。
暦年贈与とは
暦年贈与とは、1年間(1月1日から12月31日)に贈与された財産のうち110万円までは非課税、それを超える部分に対して贈与税がかかる方式のことを指します。ごく一般的な贈与税の考え方であり、多くの人が利用している仕組みです。
不動産においても登記の変更や申告の手続きが必要で、年度ごとに検討しながら贈与していくことができます。贈与税が比較的高額になりやすいものの、少しずつ贈与していくことで相続財産を徐々に移転させる戦略が取れます。
受贈者側も毎年贈与を受け取ることで、将来的な資産形成が可能になりますが、所有権をどう扱うか、税務的な証拠をどのように残すかなど注意も必要です。
暦年贈与のメリット
年間110万円の基礎控除を活用して、計画的に少額ずつ贈与することで、贈与税の負担をできる限り抑えられます。
法律的にも単純明快なしくみであるため、あまり複雑な手続きにならずに取り入れやすいのがメリットです。
徐々に子や孫へ財産を移転していくため、親としては将来の相続に備えつつ、状況に合わせて贈与のペースを決められます。
暦年贈与のデメリット
毎年こまめに贈与の手続きを行う必要があり、登記変更や税務申告などの事務作業が負担になる場合があります。
多額の不動産を短期間で移転したい場合には、贈与税を多く支払わなければならないため、必ずしも最適とは言い切れません。
贈与が本当に行われた事実を証明するため、受贈者側での銀行口座受け取りや受領書など、証拠資料を整えておく必要があります。
暦年贈与と相続時精算課税制度の違い
暦年贈与は毎年の猶予枠を活用することで、コツコツと財産を移転し、贈与税を軽くすませる方式です。一方、相続時精算課税制度は大きな財産をまとめて贈与しても、贈与時には一定額まで税金を繰り延べできる方式です。
大きな金額を一度に贈与したい場合は相続時精算課税制度が向いている場合が多いですが、将来の相続税負担が上がる可能性もあります。逆に、時間をかけて資産を引き継ぐ場合は暦年贈与が適しているかもしれません。
どちらの制度を選んでも一長一短があるので、親や家族の状況、今後の相続計画を踏まえてしっかりシミュレーションすることが肝要です。
生前贈与のメリット
生前贈与を選択するメリットは、親の判断能力がしっかりしている時期に、財産を誰にどれだけ移したいかを自分の意思で決められる点です。将来的に相続税負担を抑えられたり、遺産分割トラブルを回避しやすいという利点も享受できます。
また、早い段階で名義を移してしまえば、親の認知症などによる法的行為の制限を受けにくくなるという面もあります。子どもが不動産を活用しやすくなるなど、メリットは多方面に及びます。
さらに、家族間のコミュニケーションが深まりやすい点も無視できません。贈与の意図や将来設計を話し合うことで、トラブルを未然に防ぐ可能性が高まります。
生前贈与のデメリット
贈与税が高額になる可能性がある点が最大の懸念事項でしょう。高額な不動産を一度に贈与する場合、税金が相当かかる場合があります。
また、親が生活資金を十分に確保せずに大半の財産を贈与してしまうと、老後の生活費が不足するリスクがあります。返してもらえない可能性もあるため、慎重な検討が必要です。
さらに、贈与が完了すると、名義上も所有権が移転してしまうため、親が自由に財産を動かせません。将来的な柔軟性を保ちたいのであれば、家族信託や任意後見制度などの代替案も検討すべきかもしれません。
生前贈与のやりかた
生前贈与を行う際は、まず贈与する財産の内容・評価額、受贈者の数や関係などを整理します。その上で、暦年贈与や相続時精算課税制度など、どの制度を利用するのか判断をする必要があります。
贈与税の申告書は財産を贈与した翌年2月1日から3月15日までに税務署に提出します。不動産の場合は名義変更の登記手続きが必要になるため、司法書士や税理士に依頼するケースが多いです。
実際には金額が大きい場合もあるので、専門家と一緒に試算し、贈与税や相続税への影響を総合的に検討することをおすすめします。
どの選択肢を選ぶにしても親の意向、条件を汲んで話し合いをすること
家族でよく話し合い、お互いの希望や条件を整理したうえで、最適な方法を選択することが大切です。
制度ごとにメリットとリスクがあり、財産や家族構成は一つとして同じケースがありません。そのため、最初に家族一同でじっくり話す時間を確保し、親の希望と子どもの意見をすり合わせることが大前提になります。
「家族信託を選んだら安心」「生前贈与をすれば全て解決」といった短絡的な決め方ではなく、費用感や将来の生活設計、親の健康状態など、考慮すべきポイントは多岐にわたります。
特に、親がどんな形で物件を扱ってほしいのかという「想い」を理解することが重要です。自宅の場合は生活拠点としての意義が大きいですし、投資用不動産であれば収益確保とリスク管理にも目を配らなければなりません。
話し合う条件
具体的にどのような点について家族で合意しておくべきかを確認しましょう。
話し合いでとくに大切なのは、制度を使うタイミングと費用、親の希望条件です。親の状況や家族の仕事・住まいなどを踏まえて、いつから正式に管理を切り替えるのか、管理コストはどう配分するのかなど細部まで決めておくと、のちのトラブルを避けやすくなります。
また、親が「これだけは守ってほしい」と願うことと、「これだけはしてほしくない」という要望がある場合は、専用の文書にして明文化しておくことも有益です。後々の勘違いや対立を防ぐためにも、しっかり共有するとよいでしょう。
こうした合意形成がスムーズだと、家族信託なら契約書、成年後見なら申立書の作成、生前贈与なら贈与契約書の作成などがスピーディに進みます。誰がどう動くかあらかじめ決まっていれば、いざという時も慌てずに対応できます。
いつから託すことにするか
託す時期については、親の健康状態や意思能力の状況を最優先に考慮します。認知症が進む前に手続きを進められれば、後々の判断トラブルを回避できるでしょう。
一方で、早すぎる段階で一任すると、親がまだ存分に活用できる資産を自由に使いづらくなる可能性があります。このため、家族の協議を慎重に行い、タイミングを見極める必要があります。
今後の高齢化に伴い資産管理が難しくなりそうな時期を想定し、医師の診断や生活の実態に合わせて計画的に切り替えを準備するとスムーズです。
費用の按分負担
不動産を維持するには固定資産税や修繕費など、さまざまなコストがかかります。契約書レベルで費用の負担割合をしっかり定めておかないと、予想外の出費でトラブルが起こることがあります。
家族信託を利用する場合でも、受託者が管理費を立て替えるのか、別の家族が応分に負担するのかで方向性が異なります。成年後見制度の場合は、後見人が費用を管理しつつ、親の資産から支出するのが一般的です。
ライフステージや仕事の状況に変化があった場合の見直し方法もあわせて議論し、負担を公平に分配できるようにしておくと長期的な安心につながります。
してほしいこと
親が希望することとしては、「住み慣れた自宅をできるだけ維持してほしい」「将来は売却してホームの費用に充ててほしい」など、さまざまな可能性があります。
ここで重要なのは、親がどういう設定で家や資産を使ってもらいたいかを具体的に明らかにすることです。たとえば、家族信託の契約書に詳細を明記しておけば、子どもが運用や処分の判断をする際にも迷いにくくなります。
また、親が以前からリフォームや修繕にこだわりがある場合、後継者がその意向を尊重して物件を扱うことができるよう事前にまとめておくと、のちの不満や衝突を避けやすくなります。
してほしくないこと
一方で、親が「この物件は売らないでほしい」「土地は貸さないでほしい」といった要望を持つ場合もあります。そのような事項を明確にしておかないと、実際に管理を任された側が意図せず親の意向に反する結論を出してしまうことがあります。
家族信託や後見制度、生前贈与のいずれでも、契約文書や計画の段階で禁止事項を整理しておくことはトラブル回避の大きな要素です。
特に本人が認知症などで意思能力が低下した後では、口頭で確認することが難しくなるため、早期のうちに「してほしくない」リストを作っておくとよいでしょう。
託された不動産の管理はどうするべきか
任された物件を適切に維持・活用するための管理手法や、注意点について考えます。
託された不動産をどう管理するかは、家族の生活スタイルや資産状況、物件の属性によって異なります。賃貸で運用するのか、売却するのか、親が引き続き住むのかなど選択肢はさまざまです。
判断のポイントとしては、継続的な費用負担がどの程度発生するか、修繕義務を誰が担うか、契約更新手続きなどに要する手間がどれほどかかるかなどが挙げられます。
また、不動産会社や管理会社に運用を任せると手数料がかかりますが、空室対策やトラブル対応を一括して行ってもらえる利点もあるため、一人で抱え込まずに専門家を頼ることを検討してみましょう。
まずは現状の確認を
管理や運用を始める前に、物件の現状をまず把握しなければなりません。チェックすべきポイントを整理します。
不動産を引き継いだり管理を任されたら、まずは物件の状況を多角的に調べることが重要です。築年数、構造、リノベーション歴などはもちろん、周辺の環境や市場ニーズも合わせて把握する必要があります。
また、その物件に付帯する条件や制限(建ぺい率、容積率、接道義務など)にも注意を払うことで、将来的にどのような活用ができそうか見えてきます。既に管理会社がついている場合は契約内容をよく確認し、変更や解約が必要な場合は早めに手を打ちましょう。
物件の課題を明らかにすることで、どの程度の改善や費用がかかるかを試算しやすくなります。リフォームが必要であれば計画的に進めることができ、賃貸や売却に適した姿に近づける準備がしやすくなるでしょう。
現況
現況とは、物件が実際にどのような状態にあるかを指します。部屋の数や内装、設備の劣化具合など、詳細にチェックすることで管理や運用の方針を立てやすくなります。
特に、空室や空き家の場合は想定以上に劣化が進んでいる可能性もあり、実地調査が欠かせません。
必要に応じて専門業者に依頼し、シロアリ被害や雨漏りなど目に見えない部分の点検を行うことも検討しましょう。
場所
不動産の価値や活用方法は立地に大きく左右されます。駅やバス停からの距離、商業施設や病院、学校との関係、治安などを把握しておくことが重要です。
場所によっては、今後の家賃相場や売却価格が上昇する見込みがあったり、逆に人口減少の影響で相場が落ち込む可能性も考えられます。
ごく近距離にライバル物件が多い地域なのか、需要が安定しているエリアなのかを調べておくと、具体的な運用プランを作りやすくなります。
条件
賃貸経営を考えるなら、どのような条件で貸し出すかが重要になります。例えば、ペット可なのか、非喫煙者限定なのか、家賃はいくらに設定するのか、敷金・礼金をどうするのかなどです。
もし親が暮らす家を売却・賃貸に回す場合は、リフォーム費用や入居希望者との契約手続きなど、トータルコストを考えておく必要があります。
また、親が将来的に戻って住むプランを想定している場合、短期賃貸、定期借家契約など選択肢を検討するとよいでしょう。
リノベーションやリフォームの履歴
リフォームやリノベーションを行った記録があれば、いつどの部分をどのように改修したのかを確認しておくことが大切です。これによって建物の耐久性や省エネ性能などを判断する材料になります。
特に水回りや外壁などは修繕周期が重要で、定期的なメンテナンスが行き届いているほど資産価値を高く維持できます。
履歴が曖昧な場合は、可能なら親や施工業者に尋ね、少しでも情報を集めて将来の修繕計画を立てやすくしましょう。
修繕の状況
屋根や外壁、給排水設備など、心配な箇所がないか早めにチェックすることが管理の基本です。小さなトラブルでも放置すれば大がかりな修繕が必要になるケースがあります。
大規模修繕やリフォームにはまとまった費用がかかることが多いため、家庭の予算と照らし合わせながら計画を立てる必要があります。
親がまだ暮らしている場合は安全面に留意し、段差解消や手すり取り付けなど、バリアフリー化の検討もセットで行うと安心です。
管理会社の有無
すでに不動産会社や管理会社と契約している場合は、その契約内容や費用をよく調べる必要があります。とりわけ、管理委託料や修繕積立の扱いなどは明確化しておきましょう。
契約を継続するか、もしくは他の会社に乗り換えるかはサービス内容や実績を比較して決めるのが賢明です。
管理会社が入っていると、日常的なメンテナンスや入居者対応などを代行してもらえるため、家族の手間が軽減されるメリットもあります。
物件の課題点
老朽化や耐震性の問題、周辺住民との騒音トラブルなど、物件が抱える課題点を洗い出す作業は必須です。課題を知らないまま引き継いでしまうと、後で大きな費用負担に直面する可能性があります。
また、違法建築の疑いがある場合や再建築不可などの制限がある場合は、売却や賃貸に大きな影響を及ぼしますので、専門家の意見を早めに仰ぎましょう。
課題を明確化した上で、今後の補修計画や運用プランを作り込むことで、余計な出費やトラブルを抑えられます。
空室の場合は募集条件や近隣の相場
空室で運用したい場合は、近隣の家賃相場と募集条件を調査します。複数の不動産会社に問い合わせて、適切な家賃設定についてアドバイスをもらうことも効果的です。
ただし、あまりに相場とかけ離れた家賃を設定すると空室期間が長引く恐れもあるので、戦略的に決めましょう。
一定の家賃で賃貸を考えるなら、物件のリフォームや設備投資を検討するなど、収益と投資のバランスを計算して最適解を導くことが重要です。
まずは頼れる不動産会社に相談してみよう
状況や希望に合った提案を得るためにも、不動産会社など専門家への相談が有効です。
不動産のプロに相談すれば、地域の市況や適正家賃、売却価格の目安など具体的なアドバイスを得られます。家族だけでは判断が難しい場合にも、専門的な視点を加味することで選択肢が明確になるでしょう。
たとえば、家族信託と賃貸管理をセットで提供している会社や、相続に強い不動産会社など、得意分野をもつ業者に依頼することで相談がスムーズに進むケースがあります。
もちろん、利害関係や手数料を正しく理解することも大切です。複数社の意見を聞いたうえで、条件に合ったパートナーを選ぶと失敗が少なくなります。
まとめ
高齢の親が持つ物件を任されたときの選択肢や注意点を振り返り、適切な手段を選ぶためのポイントをまとめます。
家族信託、成年後見制度、任意後見制度、生前贈与など、それぞれの制度には独自の特徴とメリット・デメリットがあります。親の意思能力がどの程度残っているのか、どこまで自由に資産を動かしたいのかによって、適切な選択肢は異なります。
どの制度を選ぶにしても、最終的には親の希望を最大限尊重しつつ、財産を管理する人が負担を抱えすぎない仕組みを作ることが大切です。複数の制度を組み合わせる場合もあり、専門家の力を借りながら最適解を導くステップを踏むと安心です。
不動産は大切な資産であり、親世代の生活の基盤や将来の相続に関わる重要な要素です。今回紹介した選択肢や注意点をもとに、家族でしっかりと話し合い、最も良い方法を見つけていきましょう。
不動産管理のお困り事は山友管理におまかせください
山友管理では、賃貸不動産だけではなく生活の重要な基盤である建物全般のお困りごとを解決するお手伝いをおこなっております。
例えば、お部屋の内装工事・リフォーム・修繕なども承ります。
山友管理だけではなく関連会社である山友不動産・ラスコと密接な連携を行い、長年の経験やノウハウを活かし、賃貸不動産はもちろん、戸建て・マンションなど建物全般のトラブルの対応しております。
建物のことで気になることがある方はお気軽にご相談ください。

山友管理のメンテナンス・工事についてもっと詳しく知りたいかたはこちら

山友管理の不動産管理についてもっと詳しく知りたい方はこちら
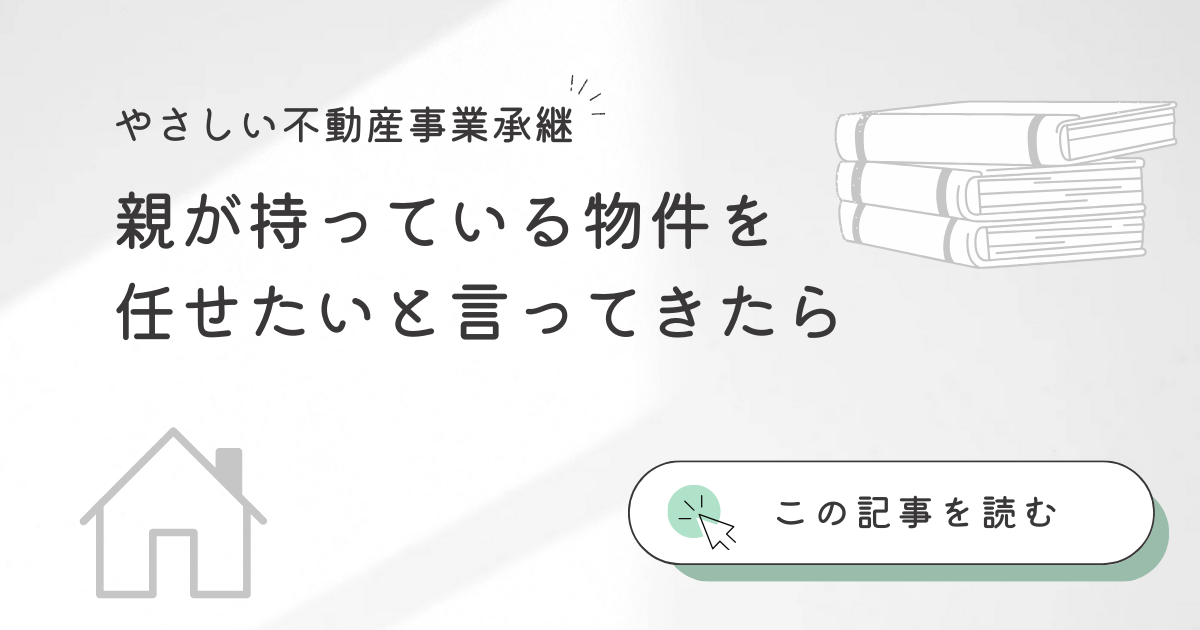
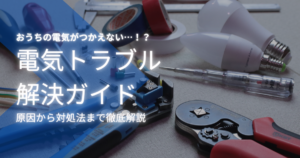
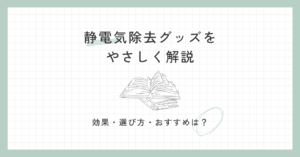
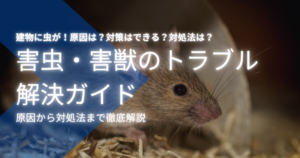
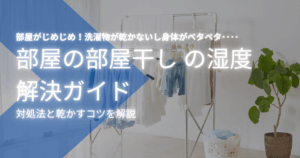


コメント