アパート経営は、一棟の建物を所有し、複数の入居者に貸し出して家賃収入を得る投資手法です。土地活用の一環として注目される一方で、空室リスクや建物の老朽化など、長期的な視点に立った運用が求められます。
少子高齢化が進むなか、需要の見込めるエリアでアパートを運営できれば安定収入が期待できるというメリットがあります。ただし、初期投資や毎月のローン返済、メンテナンス費用を正しく把握しておかないと、収益を圧迫しかねません。
本記事ではアパート経営に関する基礎知識から、よくある失敗リスク、そして長期運用を見据えた戦略までを詳しく解説します。これからアパート経営を考える方は、ぜひ参考にしてみてください。
アパート経営は本当に儲かる?基本的な仕組みと現状
アパート経営は、土地の有効活用として注目される一方で、必ずしも高収益が保証されるわけではありません。
アパート経営では、家賃収入を得ることで初期投資や融資の返済を行い、最終的に安定したキャッシュフローを目指すのが一般的な仕組みです。メリットとしては、一定の入居率を確保できれば、毎月の家賃が大きな収入源になります。また、不動産自体の資産価値が下がりにくい立地集約型の都市部や利便性の良い地域では、中長期的な利益を見込める可能性が高まります。
一方で、エリア選定や建物の設計が需要と合わなければ、空室が増えて利回りが低下するリスクがあります。特に新築物件が近隣に多く建つ場合は競合も激しくなり、家賃を下げざるを得ない状況に陥ることもあります。そのため、需要調査や資金計画を怠らず、綿密なリサーチに基づいて判断することが欠かせません。
不動産投資市場とアパートの位置づけ
不動産投資市場では、マンションや戸建てなど多様な投資商品があります。その中でアパートは、土地と建物を一括で所有するため、規模の大きい収益獲得が見込める点が特徴です。また、株式投資のように日々の価格変動で一喜一憂せずに済む、より安定性を重視した投資として評価されています。
アパートオーナーの収入実態と利回り
アパートオーナーの収益は主に家賃収入が中心ですが、それを単純に物件価格で割った表面的な利回りだけを見て判断するのは危険です。運営には管理費や修繕費、固定資産税などの諸経費がかかります。こうしたコストを考慮し、実質利回りを確認することが成功に近づくための重要なプロセスです。
戸建て・区分マンションとの比較
戸建て投資や区分マンション投資に比べて、アパート経営は一棟丸ごと所有するため、複数の入居者から同時に家賃収入を得られる利点があります。ただし、一度に空室が増えるリスクや大規模修繕のコストがまとまってかかるデメリットもあるため、投資対象の特徴を十分に理解したうえで選ぶ必要があります。
アパート経営はするなと言われる主な理由
一部ではアパート経営を避けるべきだと指摘する声がありますが、どのような観点からそういわれるのでしょうか。
アパート経営を推奨しない主な理由には、ローン返済や空室リスクなど複合的な要素が絡み合う点が挙げられます。特に低金利で融資が受けやすい環境が続くと、安易に借入比率を高めてしまい、金利が上昇したときに負担が急激に増える危険があります。
また、建物の老朽化に伴う修繕コストやサブリース契約の落とし穴なども、長期にわたる収益計画を脅かす要因となります。何らかの形で大きなリスクが顕在化した場合、資金繰りが滞り赤字経営に陥る恐れがあるため、慎重な判断が求められます。
理由1:借入金の負担と金利上昇リスク
アパート建設や購入のために多額のローンを組むケースは少なくありません。低金利だから安心と考えていても、将来的に金利が上がれば返済額が増え、キャッシュフローが一気に悪化するリスクがあります。そのため、借入比率や借入条件を慎重に検討することが求められます。
理由2:空室率や競合拡大による収益減
近隣に新築物件が増えたり、入居需要が減少したりすれば、空室率が上昇して家賃収入が低下します。特に地方都市では人口減少が顕著になり、想定していた入居率を確保できないケースが増えています。こうした状況に対応できるよう、立地選定や差別化戦略を事前に策定しておく必要があります。
理由3:大規模修繕にかかるコスト
アパートは築年数がかさむと、外壁塗装や屋根補修、配管設備の交換など大規模修繕が欠かせません。これらのコストはまとまった額になることが多く、蓄えがないと経営を圧迫します。長期的な修繕計画を立て、毎月一定額を積み立てるなどの準備を怠らないようにすることが重要です。
理由4:長期的な収益見通しの不透明さ
少子高齢化や人口動態の変化、経済状況など不動産市場を取り巻く要因は刻々と変化していきます。そのため、今は順調でも数十年先の需要を正確に予測するのは困難であり、長期的な利益計画が立てづらい面があります。こうした不確定要素を考慮したシミュレーションが欠かせません。
理由5:サブリース契約の落とし穴
家賃保証をうたうサブリース契約は、一見魅力的に映りますが、契約更新時の条件見直しで保証額が下がる例も少なくありません。サブリース会社が経営難に陥れば、支払いが滞るリスクも否定できないため、契約内容や更新時の条件を毅然とチェックする必要があります。
アパート経営をやめたほうがいい人の特徴
誰でもアパート経営が向いているわけではありません。始める前に自分の状況を客観的に確認しましょう。
アパート経営には知識や経験だけでなく、十分な自己資金やリスクヘッジの考え方も必要です。これらの事前準備が不足していると、想定外の出費やトラブルで計画が崩れ、精神的・経済的負担が大きくなる恐れがあります。
また、利回りの高さばかりを追い求め、管理やメンテナンスなどの実務を軽視すると、経営に生じる諸問題に対処できず失敗しやすくなります。自ら学び行動する意思がなければ、アパート経営は難しいものになるでしょう。
資金計画を立てずに始める人
自己資金が少ないまま高額の融資に頼ると、金利上昇や空室率の増加で返済計画が大きく狂いやすくなります。貯蓄や資金調達方法、返済シミュレーションをしっかり立てずに始めるのは極めて危険です。
事前のリスク分析・シミュレーションを軽視する人
アパート経営には、空室や家賃下落、修繕費など多くのリスク要因が存在します。こうしたリスクを数値化し、さまざまなシナリオで資金シミュレーションを行わないと、想定外の事態に直面したときの対応が難しくなります。
管理や運営に興味が持てない人
経営に必要な入居者対応やクレーム処理、改修工事の判断などを全て外部業者に任せる場合でも、オーナー自身の指示や決断は不可欠です。管理に興味がなく積極的に学ばない人は、費用対効果の悪い選択を続けてしまい、収益性を損ねるリスクがあります。
よくある失敗リスク10選とその回避策
アパート経営にはさまざまな落とし穴が潜んでいます。代表的な失敗例を挙げながら、その回避策を考えましょう。
多くの失敗は、初期段階の情報収集不足や甘い見通しから生じます。立地や需要調査、借入計画など基本的なプロセスを疎かにすると、いずれ大きな損失を被る可能性が高まります。
しかし、失敗リスクを具体的に把握し、綿密な対策を立てることで、問題の多くを未然に防ぐことができます。これから挙げる10個の事例を自分自身の計画に照らし合わせ、慎重に検討してみてください。
①高利回り物件に安易に飛びつく
表面利回りの数字が高くても、実際には家賃相場が下落していたり、空室が多かったりといったリスクが隠れている場合があります。現地調査や周辺の賃貸需要を把握し、本質的な収益性を見極めることが重要です。
②節税目的のみで始める
相続税や固定資産税の節税効果だけを期待して物件を購入すると、家賃収入の安定性や将来の物件活用など、経営の根幹を見失うことがあります。節税はあくまでも補助的なメリットと捉え、健全なキャッシュフローの確立を優先すべきです。
③サブリース契約の条件を把握していない
サブリースは空室リスクを減らす手段として有効ですが、契約内容を理解しないまま進めると、更新時の家賃設定や解除条項で大きな損失につながる場合があります。契約締結前に複数社を比較し、リスクを十分に理解することが必要です。
④借入依存が大きく返済に追われる
自己資金をほとんど使わずにフルローンなどで始めると、家賃収入が減っても毎月の返済額は変わらないためキャッシュフローが急激に悪化します。無理のない借入バランスを設定し、返済負担をあらかじめ軽減しておくことが肝要です。
⑤入居者トラブル・夜逃げを想定していない
賃貸経営では家賃滞納や夜逃げ、室内でのトラブルなどが発生することがあります。保証会社の利用や十分な敷金設定、定期的な巡回などを行い、やむを得ない事態に備えておくと被害を最小限に抑えられます。
⑥耐用年数が切れた建物の税金増大
建物が法定耐用年数を過ぎても使用は可能ですが、減価償却のメリットを活用できなくなる場面があります。また古い物件ほど修繕費や固定資産税が高くなる場合があり、長期運用の計画に大きな影響を与えます。
⑦立地・需要調査を怠り空室地獄へ
駅からの距離や周辺施設、地域の人口動態などを総合的に調査しないと、入居者がほとんど見つからず収益が大きく低下する恐れがあります。購入前に物件やエリアの競合状況を十分に調べ、需要をしっかりと確認しましょう。
⑧追加投資で借金地獄に陥る
入居率向上を狙ったリフォームやリノベーションにさらに借入を重ねると、返済負担が雪だるま式に増えていきます。投資金額と効果のバランスを見極め、計画的に行うことが大切です。
⑨リフォームコストが膨らみ収益悪化
リフォームは家賃水準や入居率を高める手段ですが、材料費や人件費が想定以上にかかり、利益を損なうケースがあります。小まめに見積もりを取って検証し、コストに見合う効果が得られるかを慎重に判断する必要があります。
⑩相続時のトラブル対策が不十分
アパート経営は相続税対策にもなる一方、財産分割で親族トラブルが起こることもあります。早めに相続人と話し合い、分割方法や買い取りの条件などを明確にしておくことで、そうした問題を回避しやすくなります。
黒字化まで何年かかる?収益シミュレーションの考え方
アパート経営の利益がプラスに転じるタイミングは、物件や融資条件によって大きく異なります。
特に初期投資が大きい場合、黒字化までに数年は見込む必要があります。建物を新築したり既存物件を購入したりする際には、融資を受ける期間や利率を想定して支出と収入を試算し、キャッシュフローが安定する時期を計算しましょう。
また、立地条件が良い物件ほど空室リスクが低く、家賃設定も高めにできる可能性があります。入居者のニーズを的確に把握し、設備充実や管理の効率化を進めることで、早期黒字化を目指すことが可能です。
単年度収支と初期投資の回収期間
1年ごとの家賃収入と経費を明確にし、何年後に初期投資額を回収できるかを数値化します。途中で空室が発生したり、大きな修繕が入る可能性もあるため、過度に楽観的なシミュレーションにならないよう注意が必要です。
利回り計算と期間短縮のポイント
物件価格に対して得られる家賃収入の割合が利回りの基本指標です。なるべく高い利回りを目指すには、立地や物件状態を最適に組み合わせ、入居率を高く維持する管理方針が求められます。そこに加えて、金利や経費の見直しも早期黒字化のポイントです。
自己資金を増やすメリット
自己資金を多めに用意しておくと、ローン返済の負担が軽くなり、キャッシュフローに余裕を持ちやすくなります。その結果、リフォームや修繕に柔軟に対応できるため、空室リスクへの対策もしやすくなり、結果として黒字化のスピードを高めることにつながります。
30年後を見据えたアパート経営の戦略
アパート経営は長期にわたる投資です。将来の老朽化や市場変化にどう備えるかが、成功を左右します。
30年先を見据えたとき、建物の耐久性や修繕頻度、居住者ニーズの変化など、検討すべき課題は多岐にわたります。修繕渡りに計画的な積立を行うほか、定期的に建物の評価を見直し、必要があればリノベーションを実行して物件価値を高めることが大切です。
また、立地によっては人口減少や社会構造の変化の波を受ける可能性があります。市場の動向を注視し、一定期間後には売却や建て替え、再投資などを柔軟に選択することが、長期的な安定収益の鍵となります。
建物の老朽化とリノベーション対策
築年数が経るほど修繕コストは増える傾向にあり、放置すると入居者離れにつながります。リノベーションを定期的に実施し、物件の使い勝手やデザインを最新化することで、長期間にわたり魅力的な物件として運営を継続できるでしょう。
売却・建て替え・再投資の出口戦略
築年数が進んで修繕費用がかさむ時期に、物件を売却して他の不動産へ投資する戦略も選択肢の一つです。また、更地にして建て替えを行うことで、未来の需要に合ったアパートに生まれ変わらせる方法も考えられます。いずれも市況や資金状況を見ながら最適なタイミングを選ぶことがポイントです。
市場変化や金利の影響を読んだ長期プラン
不動産は経済状況や金利政策の影響を受けやすいため、30年という長期で考えるなら、複数のシナリオを想定した経営プランを用意する必要があります。低金利が長く続いた後に急な金利上昇が起きた場合の対策や、需要の減退時に柔軟に対応できる仕組みづくりが肝要です。
まとめ・総括
アパート経営の成否は、事前の計画や情報収集、そして長期的な修繕・資金対策にかかっているといえます。
安易に始めると思わぬリスクに直面し、収支がマイナスに転じる事態を招きかねません。しかし、需要のあるエリアで計画的に運営し、空室リスクや修繕費を見据えた投資を行えば、安定的な家賃収入や資産形成が期待できる可能性も高まります。
長期的には築年数や市場環境の変化に柔軟に対応し、出口戦略も含めた複数のシナリオを用意しておくことが重要です。自分の目的や資金力を見極め、正しい情報と専門家のアドバイスを活用しながら、納得のいくアパート経営を行いましょう。
建物のお困り事は山友管理におまかせください
山友管理では、賃貸不動産だけではなく生活の重要な基盤である建物全般のお困りごとを解決するお手伝いをおこなっております。
例えば、お部屋の内装工事・リフォーム・修繕なども承ります。
山友管理だけではなく関連会社である山友不動産・ラスコと密接な連携を行い、長年の経験やノウハウを活かし、賃貸不動産はもちろん、戸建て・マンションなど建物全般のトラブルの対応しております。
建物のことで気になることがある方はお気軽にご相談ください。

山友管理のメンテナンス・工事についてもっと詳しく知りたいかたはこちら

山友管理の不動産管理についてもっと詳しく知りたい方はこちら

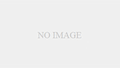
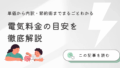


コメント