2025年に実施が予定される令和7年度の税制改正は、多岐にわたる項目が盛り込まれています。本記事では所得税や相続税を中心に、改正のポイントをわかりやすく整理して解説していきます。防衛費確保などの大きな政策から個人の控除額調整まで幅広い内容が含まれており、特に相続税 改正 2025 年に関する動きは資産承継の面で注目度が高まっています。最新の改正情報を押さえて、早めの対応や対策を進めていきましょう。
令和7年度税制改正大綱のポイント
令和7年度税制改正大綱にはさまざまな政策目的が反映され、基本的な考え方や防衛力強化などの施策が示されています。
まず、令和7年度の税制改正大綱では、経済状況や長期的な社会保障費の増大に対応するための基本方針が打ち出されています。国内外の経済動向に応じて財政安定と成長促進の両立を図ることが重要視され、所得税や法人税をはじめとする各税目における見直しが継続的に行われています。今後の景気変動に備えつつ、社会保障制度を支える安定した税収確保がポイントとなるでしょう。
一方、税務関連の手続き上の負担軽減も議論の焦点になっており、各種書類の電子化やデジタル手続きの推進が進められています。行政コスト削減や申告書類の簡素化を進めることで、納税者がスムーズに対応できる環境をつくる狙いがあります。結果として、社会や経済における変化を踏まえた税制の柔軟性と効率性が求められているのです。
税制改正の基本的考え方と背景
税制改正の背景には、高齢化の進行と社会保障給付の増大があります。加えて、新たな雇用形態や働き方の変化にも対応していくため、所得税の仕組みをより負担能力に応じたものへと進めようとする考え方が示されています。こうした基本的考え方をもとに、政策実現と財源確保の両立を図るのが令和7年度税制改正の大きな方向性といえます。
防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
防衛費の拡充に向けて追加的な財源をいかに確保するかが、今回の税制改正において重要な議題となっています。所得税や法人税の一部調整によって財源を捻出する案が検討されており、国際情勢の変化を踏まえた安定財源の確保が急務だという議論が進められています。こうした政策が個人の税負担に与える影響も注目されているため、今後の国会審議の動向に留意しておくことが大切でしょう。
扶養控除・所得控除の改正動向
物価上昇や労働環境の変化に対応すべく、所得控除の再調整や就業促進を目的とした改正が行われます。
近年の物価上昇局面では、実質的な購買力が下がる一方で個人の税負担が増えるリスクが高まります。そのため、所得控除に関しては低所得層への配慮や就業調整を緩和するための施策が検討されています。特に若年層や子育て世帯への支援を強化する方向が打ち出されており、実生活とのバランスを考慮した改正項目が多いのが特徴です。
さらに、給与所得者がより働きやすくなる環境を整えるため、給与所得控除や配偶者・扶養控除の収入要件の見直しもポイントです。こうした改正は家計の実情を反映し、就業機会を広げる一方で過度な税負担を防ぐ狙いがあります。今後の詳細な法令化に向けて注意深く動向を見ていく必要があるでしょう。
物価上昇局面における税負担の調整および就業調整への対応
物価の上昇により家計が圧迫されやすい状況を踏まえ、控除額の上積みや収入基準の引き上げが検討されています。就業調整に関しても、配偶者特別控除が働き方に与える影響を小さくするように要件を再定義する動きがみられます。こうした調整で生じる社会保障費とのバランスや、財政全体に与える影響にも注目する必要があるでしょう。
基礎控除の引き上げ
個人所得税の基礎控除額を増やすことで、主に中低所得者層の負担を軽減する措置が計画されています。現在の経済情勢では、最低限の生活を維持するための支出が増加する傾向にあるため、より多くの人がこの引き上げの恩恵を受けられることが期待されます。特に一人親世帯や若い世代にとっては重要な改正項目となるでしょう。
給与所得控除の引き上げ
給与所得控除の拡大はサラリーマン世帯の税負担を和らげる重要なポイントです。現在は収入に応じて控除額が変動する仕組みですが、更なる上限拡大や段階的な見直しが検討されています。特に物価高騰が家計を圧迫する中で、給与所得控除の充実は就業意欲を維持するうえで効果が期待できます。
特定親族特別控除の創設
特定の扶養親族がいる家庭に対して、追加的な控除を設ける仕組みが新たに設計されようとしています。多子世帯や高齢親族を支援する必要がある家庭など、特に負担が大きい層に焦点を当てることで、生活を安定させる効果が見込まれます。今後の詳細要件や適用範囲次第で、控除額のメリットがどの程度になるか注目されています。
配偶者・扶養控除の年収要件の引き上げ
従来、配偶者や扶養家族に適用される控除は年収要件を下回る場合に恩恵が大きい仕組みでしたが、その要件が引き上げられる方向にあります。これにより、パートやアルバイトなどで働きながらも、より高い収入水準を得ても控除が適用されるケースが増えそうです。就業調整を気にせず、家計にプラスになる働き方を選択しやすくなる点がメリットといえます。
個人住民税の給与所得控除引き上げ
所得税だけでなく住民税においても給与所得控除の引き上げが行われる見通しです。これによってニュースや国政レベルだけでなく、自治体レベルでも納税者の負担軽減が期待されています。地域の財源不足と両立しながら、どこまで住民税の控除を手厚くできるかが鍵となるでしょう。
投資に関する税制
投資促進策としてNISAや確定拠出年金制度(DC/iDeCo)の制度拡充も大きなポイントです。少子高齢化による年金財政への懸念が強まる中で、個人が自主的に資産を増やす仕組みへの注目度が高まっています。特に長期投資やドルコスト平均法など、幅広い投資スタイルを容認する非課税枠の拡大が焦点となりそうです。
NISAの利便性向上
NISAの非課税投資枠拡充や制度の簡素化が進められています。これにより、投資初心者が少額からでもスタートしやすくなり、中長期的に資産形成を図ることが期待されます。また、金融リテラシーを高めるための情報発信やサポート体制の充実も重要な課題となっています。
確定拠出年金制度(DC/iDeCo)の拡充
老後の生活資金を自助努力で確保するため、確定拠出年金の掛金上限の引き上げや加入者の拡大が予定されています。特に企業型DCの導入促進が焦点とされ、より幅広い層が税制優遇を享受しながら老後資産を積み立てられる環境が整備されつつあります。掛金の上限が増えることで、まとまった金額を長期的に運用できるメリットが期待されています。
子育て世代に関する税制
少子化対策のひとつとして、子育て世代への税制優遇策も引き続き拡充される見込みです。生命保険料の控除や住宅ローン控除など、生活基盤を安定させる仕組みは子育て中の家庭にとって大きな支えといえます。控除適用の条件や期間がどう変わるか、詳細を確認して早めの計画を立てることが大切です。
子育て世帯の生命保険控除の拡充
子育て家庭のリスクヘッジを支援する目的で、生命保険料の控除枠を拡大する案が示唆されています。子どもの教育資金や生活費がかさむ時期において保険への加入を促すことで、万が一の備えを強化できるメリットがあります。家計への負担を抑えつつ、より手厚い保険を選択しやすくなる点が注目されています。
子育て世代の住宅ローン控除の延長
子育て世帯向けの住宅ローン減税について、適用期間の延長や控除率の見直しが検討されています。マイホーム取得時の初期費用負担を軽くする意図があり、これによって家計への大きな安心材料になるでしょう。物価や金利動向にも左右されるため、早めに情報を収集して住宅取得計画を立てることが重要です。
子育て対応リフォームの特別控除の延長
新築だけでなくリフォームにも焦点が当たり、子育てに配慮した間取り変更やバリアフリー化などに対する特別控除が延長される見通しです。これまで家族構成の変化で住まいに対するニーズが大きく変わるタイミングには、補助金などのサポートが利用されてきました。今後も継続することで、住環境を整えながら家計を守る制度の活用が期待されます。
退職所得控除の調整規制の見直し
退職金に対する課税の公平性を高めるため、退職所得控除に関わる適用範囲や金額の見直しが検討されています。特に早期退職や転職が一般的になりつつある社会情勢を受けて、多様な働き方を踏まえた税制整備が求められています。結果として、退職後の生活設計にどのような影響が出るかを見極める必要があるでしょう。
各種証明書の提出省略
税務手続きを効率化するため、オンライン申請やマイナンバー活用の拡大により、紙ベースの証明書提出を省略する取り組みが加速しています。証明書取得の手間とコストを削減し、行政全体のデジタル化を促進する施策として期待されます。将来的にはさらに手続きが簡素化され、納税者にとってもメリットが増える見通しです。
相続・贈与税関連の主な改正項目と要望
資産承継をめぐる環境変化に対応するため、相続税・贈与税の納税猶予や非課税制度などが見直されます。
特に2025年の相続税改正は、結婚・子育て資金の一括贈与税の非課税措置延長など、若い世代への資金移転を促進する施策が焦点となっています。非上場株式や農地に関わる納税猶予制度の改正も、事業承継や地域の活性化を図る上で重要な要素です。物納制度の要件緩和によって納税者にとって選択肢が増えるかどうかも注目されています。
結婚・子育て資金の一括贈与税の非課税措置延長
結婚・子育て資金の贈与税非課税措置については、2027年3月31日までの延長が盛り込まれる方向です。これにより、若い世代が大きなライフイベントを迎えるタイミングで祖父母や両親から資金援助を受けやすくなります。少子化対策の一環としても位置づけられており、資金の早期移転による経済的な安心感が得られるでしょう。
農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し
農地や山林の相続税・贈与税納税猶予制度では、新たに介護医療院への入所が特例の適用条件に加わる方向です。こうした改正によって、高齢化が進む農業従事者の後継者不足対策や農地の集約化を促す狙いがあります。従来より複雑だった要件緩和にも期待が寄せられ、農家や後継者にとっては事業継続がしやすくなる可能性があります。
個人事業用資産や非上場株式等の納税猶予特例とその改正
個人事業資産や非上場株式にかかる贈与税の納税猶予制度では、受贈者の要件緩和や対象範囲の拡充が検討されています。後継者が資格を有する場合に限り適用されていた枠組みを広げることで、事業承継をスムーズに行える環境が整えられる見通しです。地域の中小企業や家業の存続にとって、税制面からの支援は欠かせない要素となっています。
相続登記等の登録免許税の免税措置
相続に伴う土地や建物の登記手続きを促進するため、登録免許税の免税措置がさらに2年間延長される見通しです。空き家問題や土地の有効活用に向けて、相続時の所有権移転をスムーズに行うための施策が進められています。相続登記を怠ると将来的に権利関係が複雑化するため、この免税措置が引き続き維持されることは重要な意味を持ちます。
相続税の物納制度の改正ポイント
相続税の物納制度については、物納許可基準の見直しや申請手続きの簡素化が検討されています。従来、物納対象となる不動産や有価証券には条件が多く、実際に活用しにくい面がありました。今回の改正で取扱いを柔軟化することで、納税者の負担が軽減されるとともに、長期延納との組み合わせがしやすくなることが期待されます。
マンション固定資産税に係る特例措置の延長
マンションを中心とした固定資産税の特例措置が延長される見込みです。住宅需要や都市部の居住環境を確保する目的から、マンション購入を検討する層には追い風となるでしょう。固定資産税の負担が軽減されれば、購入後の資金計画が立てやすくなり、資産活用の幅も広がると考えられます。
不動産投資における影響は?
改正による所得控除や相続税の動向は、不動産投資の収益構造や相続対策にも影響を与えます。
不動産投資においては、相続時の納税猶予や所得税控除の動向が投資計画に大きく左右するため、2025年以降の改正内容をしっかり把握することが重要です。とりわけ相続税・贈与税の非課税制度や特例措置の延長が、物件の取得や資金移動のタイミングに影響を与えます。長期的には不動産価格や賃貸需要にも連鎖し得るため、税制と市場動向の両面から判断することが大切です。
その他の関連改正:中小企業支援や不動産・金融取引
中小企業向けの支援策や投資促進を目的とした税制の改正も多く盛り込まれています。
企業規模に応じた軽減税率の特例や、中小企業の生産性向上を狙う税制優遇措置の延長など、事業活動を後押しする動きが強化されています。これらの制度は地域経済の活性化にもつながり、特に地方の事業承継や新規事業の立ち上げを支援する意味合いが大きいといえます。金融取引面でもエンジェル税制の拡充など、スタートアップ投資を促す施策が目立ってきました。
こうした改正は、結果的に雇用創出や税収の安定につながると考えられています。中小企業の資金繰りをサポートし、リスクマネーを呼び込みやすい環境を整えることで、経済全体に好循環を生む狙いがあります。具体的な適用条件や期限が大きく左右するため、事業者は最新情報を確認しつつ、活用を検討する必要があります。
中小企業の軽減税率の特例の縮減
これまで中小企業を支援するために設けられてきた軽減税率の特例が、段階的に縮小される可能性があります。財政健全化との兼ね合いなどから、適用条件の厳格化や期限の短縮が検討されることもあり得るでしょう。あらかじめ軽減措置に依存しすぎない経営計画を組むことが一段と重要になってきます。
中小企業経営強化税制の見直しと延長
生産性向上につながる設備投資を行った企業に対して、税額控除などの優遇措置を与える中小企業経営強化税制が再評価・延長される見通しです。特にIoTやDX(デジタルトランスフォーメーション)関連の設備導入を推進し、業務効率を高める企業を後押しする狙いがあります。時代の要請に即した対象範囲の拡充により、さまざまな業種が恩恵を受けられる可能性があります。
中小企業投資促進税制の延長
中小企業が新たな設備を導入する際、一定の税制上の優遇を受けられる投資促進税制の延長も検討されています。これは地域における経済活動を活発化させ、雇用の維持・創出を図る上で効果的です。投資回収期間の見通しが立てやすくなるため、新分野への進出や新製品の開発にも取り組みやすくなるでしょう。
エンジェル税制の拡充
ベンチャー企業やスタートアップへの投資を促進するためのエンジェル税制について、要件の緩和や控除拡充が見込まれています。特に成長が期待される分野で新しい技術やサービスを提供する企業を支援することで、大きなイノベーションを生み出す可能性があります。個人投資家に対する優遇措置が拡大すれば、多様な資金調達手段が確立され、起業環境のさらなる整備につながるでしょう。
エンジェル税制とは?
エンジェル税制は、スタートアップ企業などに個人投資家が投資した際に所得控除や譲渡益控除などの優遇措置を受けられる制度です。これにより、リスクの高い投資へのハードルを下げ、ベンチャー企業への資金流入を高める狙いがあります。社会的にも新規事業の創出や地域活性化を促す効果が期待されており、拡充によりさらなる投資拡大が期待されています。
まとめ・総括
所得税や相続税の改正ポイントは個人や企業の経済活動に大きく影響します。最新情報を入手し、早めの対策を行うことが重要です。
2025年に向けて大きく変わる可能性のある相続税や所得税の改正は、個人のライフプランや中小企業の事業計画に直接影響してきます。特に相続税 改正 2025 の動向は、結婚・子育て資金や農地承継に関する非課税措置の延長をはじめ、資産承継を円滑にするための重要なポイントです。税制改正の具体的内容が固まる時期に合わせて、専門家への相談や事前準備を進めることで、制度の恩恵を最大限に活用できるでしょう。
建物のお困り事や資産のご相談は山友管理にお任せください。
賃貸の管理だけでなく建物お困り事、資産形成でお困りの際は、山友管理にご相談ください。
ファイナンシャルプランナーをはじめとする私たちの経験豊富な専門チームが、状況を細かく分析し、最適な解決策を提供いたします。
お客様のご希望あわせた士業の斡旋も行っております。
些細な疑問やちょっと気になることなど、お気軽にお問い合わせください。

山友管理のメンテナンス・工事についてもっと詳しく知りたいかたはこちら

山友管理の不動産管理についてもっと詳しく知りたい方はこちら
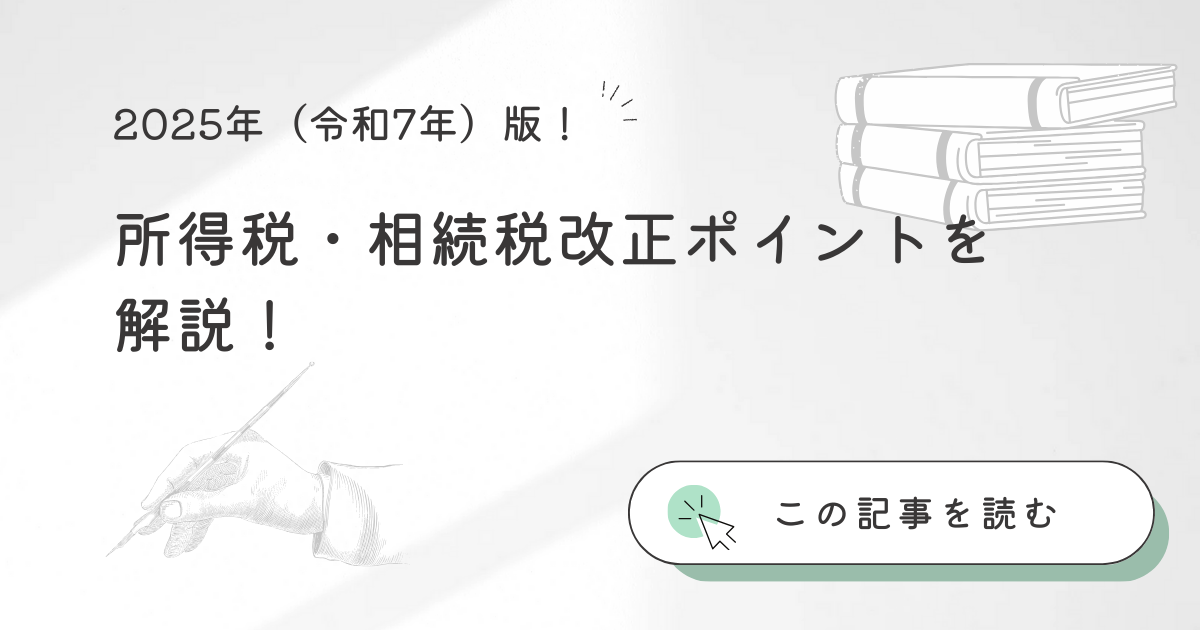
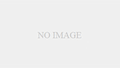
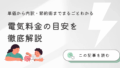
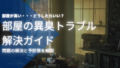

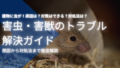

コメント